「興味があって始めたのに、気がつくとやめてしまっている…」
「続けられない自分にがっかり」
「続けようと思っていたのに飽きてしまった」
こんなことはありませんか。
ひとつのことを長く続けたいと思っていても、飽きてしまったり、いつの間にかやらなくなっていたりすることは、誰にでもあることですよね。
特にHSPやHSS型HSPの気質を持つ人は、感受性や好奇心が豊かな分、刺激に疲れやすく、飽きやすい傾向があるため、ひとつのことを長く続けるのが難しいと感じることが多いかもしれません。
でも、HSPやHSS型HSPだからといって、何も続けられないわけではなく、実際に、ひとつのことを長く続けている人もいますよね。
では、どんなときに長く続けることができるのでしょうか?
この記事では、HSP・HSS型HSPの方向けに、無理なく続けられる「自分に合った対象」の見つけ方と、「続けられるやり方」のヒントをまとめました。
「続ける=正解」って本当?|“続けなきゃ”という思い込みを手放す
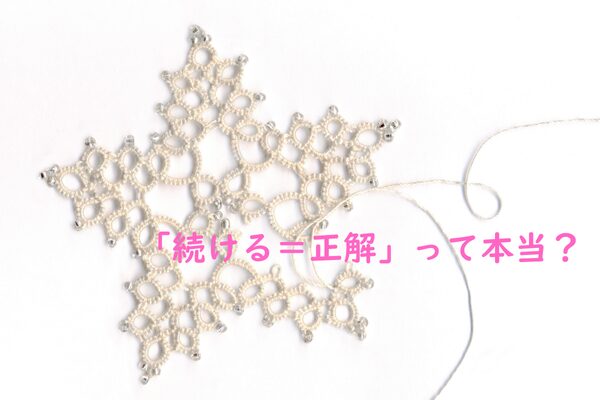
「続けることが大事」「継続は力なり」──そんな言葉をよく聞きますね。
ビジネス書や自己啓発本でも「続けた人だけが成功する」と語られがちです。
例えば、ベストセラー『GRIT やり抜く力』や『習慣が10割』などでも、「継続することが成功のカギ」と語られています。たしかに、それでうまくいった人も多いのでしょう。
確かに、ひとつのことを続けて成果を出す人はすばらしけど、それはすべての人にとっての“正解”とは限りません。
場合によっては、「続けない」方が自然なこともあるかもしれません。
「続かないこと」=「失敗」や「根気のなさ」ではないと思うのです。
HSS型HSPの場合、興味をもった新しいことに挑戦して”自分の興味”や“やりたい気持ちを満たす”のも大事なことだし、HSPの場合、合わないと感じて手を止めるのは自分の心や体を守るために必要なことです。
「ひとつのことを続ける」ことは必ずしも正義ではありません。
それでも「何か続けたい」と思うあなたへ
そうは言っても、「ひとつのことを長く続けたい」「続けられる何かが欲しい」と願う方は多いと思います。
何かを長く続けていくことは、心のよりどころになったり、経験をより深く味わえるきっかけになったりと肯定的な面がたくさんあります。
そこでここからは、「長く続けられるものがほしい」と思うHSP・HSS型HSPのために、長く続けられる対象との出会い方や、続けていくための工夫について書いていきます。
HSP・HSS型HSPが「続けられない」と感じやすい理由

「ひとつのことを続けられない」と悩むのは、HSPやHSS型HSPに限ったことではありません。
誰にでも、やる気が途切れたり、途中でやめてしまう経験はあるものです。
ただ、HSPやHSS型HSPが“続けられない”と感じやすいのには、気質による理由もあります。
それは「意志が弱いから」「努力が足りないから」ではなく、もともとの特性としてそうなりやすい面があるのです。
まずここでは、HSPとHSS型HSPそれぞれに「続けづらさ」につながりやすい気質的な背景についてみていきましょう。
HSPの場合:刺激に弱く、完璧主義や罪悪感で止まってしまう
HSPは感受性が高く、外からの刺激を強く受けるため、心身が疲れやすい傾向があります。
その結果、
- 少し頑張る → 疲れる → 中断する
- 中断すると「やっぱり自分はダメだ」と責める
- その自己否定感で、再開する気力もわかない
このようなループに陥ってしまうことがあるかもしれません。
さらに「ちゃんとやらなきゃ」「最後まできちんと続けなきゃ」という完璧主義の傾向が足をひっぱって、余計続けにくくなる場合もあります。
また、本当は小さな一歩でよいのに、ハードルを上げすぎると続けられなくなってしまう場合もあるようです。
HSS型HSPの場合:「新奇性の追求」と「退屈しやすい」特性をもつ
HSS型HSPの代表的な特性には、「新しい経験や新奇性を追求すること」と、「飽きっぽさ・退屈しやすさ」の2つが含まれています。
特にこの飽きっぽさは、HSSの特徴的な特性のひとつです。
さらに、HSS型HSPは何かをマスターするのが早く、短期間である程度できるようになってしまう人も少なくありません。
その結果、次のようなことが起こりがちです。
- 新しいことに興味を持つと、すぐに行動して熱中する
- 最初はワクワクして始めても、ある程度できるようになると刺激がなくなり飽きてしまう
- 飽きるころには、また別の対象を見つけて「やってみよう」とワクワクする
こうしたサイクルを繰り返すうちに、熱中して始めたものをあっという間に手放してしまい、「また続かなかった…」と落ち込むこともあるかもしれません。
周囲からも「え、あんなに夢中だったのに?」と驚かれたりします。
このような“飽きっぽさ”は、一見するとマイナスに思えるかもしれません。
ですが、HSS型HSPは強い好奇心や深く掘り下げる力もあわせ持っており、その結果、多彩な経験や視点を手に入れられるというプラス面もあります。
だからこそ、この特性を理解し、うまく付き合っていくことが大切です。
HSP、HSS型HSPだから続けられないということはない

もちろんHSPやHSS型HSPでも、ひとつのことを長く続けている人はいます。
たとえば──
- 子どものころから書道を習っていて、大人になっても自分の表現手段として大切にしている
- 幼い頃からずっと音楽がそばにあって、形を変えながらも長く関わり続けている
- 読書や文章を書くことが、気づけば何年も習慣になっている
作家や音楽家などのクリエイター、さまざまな分野で活躍するプロフェッショナルの中にも、もちろんHSPやHSS型HSPの方は存在します。
彼らは、ひとつのことを長く続けてきたからこそ、プロとして活躍していると言えます。
(ネットで「HSP 有名人」「HSS型HSP 有名人」などと検索すると、多くの例が出てきます)
つまり当然ですが、HSPやHSS型HSPだから一つのことを続けられないわけではないということです。
では、「続けられる場合」と「続けられない場合」では、何が違うのでしょうか?
その原因として考えられるのが、続けようとする対象の選び方と、続け方です。
続けられるものを見つける2つのヒント
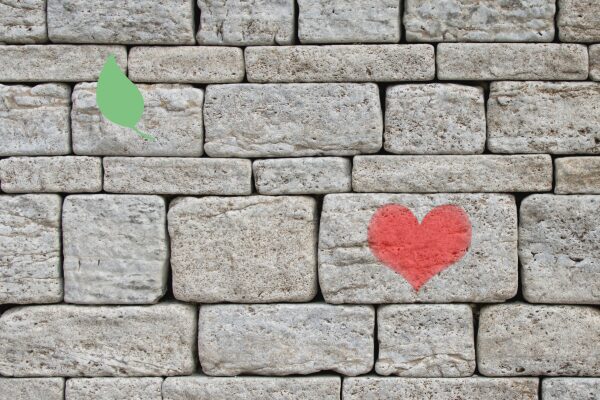
「続けられる」理由のひとつとして、そのものが自分自身の感性や探究心、創造性とうまくかみ合った時に、続けられるようになるということが挙げられます。
それは、例えば自分にとっての“核”に触れるものである場合に自然と長く続けられるのではないでしょうか。
はじめから「これだ!」と確信できなくて、あとから振り返ってみると「ずっと好きだった」「いつもそばにあった」と気づくようなものかもしれません。
では、そんな長く続けられるような対象は、どうやって見つければいいのでしょうか?
ここからは、そうした「続けられるもの」との出会い方について、2つのヒントをご紹介します。
自分の中の「核心のモチベーション」に触れているかどうか
何かを続けられるかどうかは、自分の中にある“核心のモチベーション”に触れているかどうかがひとつのカギになります。
核心のモチベーションとは何か?
それは、自分の内側から自然と湧き上がってくる“やる気の源”のようなものです。
「夢」や「目標」のような大きなものとは限りません。
むしろ、「小さなモチベーション」とも呼べるような、自分を突き動かす“細かな欲求”にこそヒントがあることも多いのです。
その一例として、こんな感覚があるかもしれません。
- 物をきれいに並べるのが好き
- ひとりで集中して作業するのが落ち着く
- 洗練されていないものを見ると、つい整えたくなる
- 手を動かして何かを作ると満たされる
そんなささいな「好き」や「気になる」感覚の奥に、あなたが無理なく続けられるもののヒントが隠れています。
鳥が好き、星が好き、音楽が好き、ガーデニングが好きという大きなモチベーションがあるとしたら、それに対してどんなふうに取り組むのが好きなのか?という小さなモチベーションを細かく見ていくことで、自分の核心に触れるモチベーションに近づくことができます。
たとえば、鳥が好きな人でも、その関わり方にはさまざまなタイプがあります。
例えば、
観察するのが好き、写真を撮るのが好き、自然の中で人と一緒に鳥を見るのが好き、鳴き声を聞き分けるのが面白い…
音楽が好きだとしたら、
演奏するのが好き、聴くのが好き、音に合わせて体を動かすのが好き、つい聴いてしまうのはメロディ?リズム?ハーモニー?、音楽が自分の体にどんな影響を与えるか?…
などなど、いろんなモチベーションが考えられます。
このように、大きな「好き」だけではなく、その中にある“どの要素が好きか”を掘り下げることが、自分の“核心のモチベーション”に近づくひとつの手段になります。
外からの評価や流行、「やらなきゃ」という義務感から選んだことは、どこかでズレが出てしまいます。
最初は頑張れても、「自分をその気にさせるもの」でなければ続けられなくなります。
一方で「核心のモチベーション」に触れるものは、「やらなきゃ」ではなく「やりたいからやっている」「やらずにいられない」と感じられて、続けられるものになるはずです。
「核心のモチベーション」に触れるものを探すためには、自分の中の小さなモチベーションを集めてみてください。
子供の頃からなんとなくやっているもの、ちょっと好きだったものの中で、その中の何が好きなのか、少し細かく掘り起こしてみてはどうでしょう。
小さなモチベーションの組み合わせから、続けられるものが見つかるかもしれません。
「ちいさなモチベーション」については次の記事でも紹介しています。
経験の中で「核心に触れるもの」を探す方法
「これが私の“核心”だ!」と思えるようなものには、出会えたらラッキー。でも、実際にはそう簡単には見つからないのでは…と思うかもしれません。
でも、これまでなんとなくやっていたことの近くにヒントがあることもあります。
「ぴんとこないけどやっている」ものの近接領域を探す
例えば、「やっているけど、なんとなくピンとこない」ものならあるという場合。
もしかしたら、“核心の隣”のことをやっているのかもしれません。
自分の核心に近い、いわば“近接領域”のことをやっている状態です。
自分の核心の近接領域に、よく知られたメジャーなものがあったら、最初はそれをやってみるかもしれない。
その場合、自分の核心に近いから、そこそこうまくできて、結構上達するかもしれない。
でも、そんなに夢中になれない、ぴんとこない、突き抜けられない…ということになるかもしれません。
もし、何となくやっているけど”これじゃない”というものがあったら、その近接領域にもっと興味を引くものがないか探して見るのはひとつの手です。
私が好きな音楽家の話ですが、
南理沙さんはオーボエ奏者からクロマチックハーモニカに転向された方。同じく、山下 伶さんはフルートからクロマチックハーモニカに転向。転向された結果、お二人とも、日本でよく知られるクロマチックハーモニカの演奏家として活躍されています。
また、宮崎駿さんは、漫画家志望から アニメーションの世界へ入られたそうです。
静止画より「動く世界をつくること」により強く惹かれたとのことで、近接領域から自分の核心のモチベーションの領域に入り、ご自身の感覚に従うことによってすばらしいアニメを生み出すに至ったのではないかと思いました。
例がすごい方々のお話になってしまいましたが、どんなレベルでも近接領域から自分の「核心」に近づくという点では同じではないでしょうか。
(将来、高いレベルに到達しないとも限らないですよね!)
もし、”何となくやっているけどぴんとこない”というものがあったら、その近接領域に興味を引くものがないか調べてみてみてはどうでしょうか。
経験の中で「続いていないようで、実は続いているもの」を探す
もうひとつは、自分の経験を振り返って、続いていないように見えるものの中に、実はずっとつながっているものがないか探すことです。
もしあったらそこから、あなたの核心に触れる「続けられるもの」が見つかる可能性もあります。
たとえば──
- 子どものころから何となく好きだったこと
- 間があいても、何度も戻ってくること
- 仕事や趣味、形は変わってもずっと身近にあったテーマ
たとえば「音楽」が好きな場合。
演奏することはやめたけれど、今でもよく聴く/リズムに反応して体を動かす/音楽が流れる空間が心地よい──そんな形で関わり続けている人もいるはずです。
それなら、「楽器の演奏やってみたけど続かなかった」で片づけるのは、もったいないかも?
また、「言葉」が好きなら…。
読書、詩作、文章を書く仕事、SNSでの表現など、時代や自分の成長に合わせて形を変えながら続いていることもあるかもしれません。
「いろいろやったけど、続かなかった」というより、言葉という軸でみるとずっと続いていると言えます。
そのように見ていくと、続いているものの「本質」は、案外シンプルで一貫していることがあります。
- 音楽
- 言葉
- 人に伝えること
- 探求すること
- 手を動かして作ること など
自分の中で細く長く続いているもの。
それが何なのかを見つけられたとき、あなたにとって自然に続けられるもののヒントがみつかるかもしれません。
私(HSS型HSP)の場合の「実は続いていたもの」
私の例を紹介します。子供の頃からいろいろなことをしてました。
- 5歳~14歳までピアノを習っていた。
- 小学校では器楽部、リコーダー部、中学では合唱部に在籍していた。
- 高校~大学生の頃、ショパンやベートーヴェンの有名なピアノ曲に勝手に挑戦していた
- 38歳、ダンスを始めて、特にタップダンスとロックダンスに夢中になった。
(ダンスに役に立つかもと思って、パーカッション、ドラムやヴォーカルも少し習っていた)
ダンスは10年くらいて挫折。 - 52歳どうしてもリズムが好きであきらめられず、パーカッションとドラムを始めた。
専門学校で学び、今も続けている
こう書くと、「音楽が好きだったのね!」と思うかもしれないけど、私自身は「音楽が好き」という認識は全然なく…。
子供の頃のピアノは特に好きではなく習い事としてただ続けただけ、器楽もリコーダーも合唱も、部活をする必要があったから入っただけで、やりたかったわけではなかったです。
でも、ダンスを始めてかなりたってから、
先生に「ことさとさんは音楽が好きなんだね!」と言われたり、「ほんとにリズムが好きだね!」と言われて、初めて「そうなの?!私って音楽が好きだったの?」と驚きました。
「このくらいでも、”好き”と言っていいの?」とも思いました。
ただ、私の核心のモチベーションは「リズム」だったので、リズムに行きつくまで、その周辺のことをいろいろやっても”当たってる”感じがしませんでした。
その時々で、興味をもったもの、惹かれたものをやってきた結果、「リズム」にたどり着きました。
パーカッションとドラムを始めて8年、これがほんとにゴールかわからないけど、子供の頃から音楽はずっと続けてきたことが、リズムにつながっていました。
そうして見つけた音楽とリズムは、今は自分のアイデンティティ(自分が自分であると言えるもの)のひとつとして、心のよりどころになっています。
「続けられる」核心のモチベーションを探すコツ
「続けられるもの」を探すときに、この辺がコツかなぁ?と思うと点をまとめてみました。
私もまだまだ道半ばで、「こうすれば見つけられる!」とは言えませんが、この辺が大事かも?と思うところです。
①自分にぴったり合ったものを見つけたいという気持ち
ひとつめは、「自分に合ったもの、続けられるものをなんとか見つけたい」と思う気持ちです。
情熱、思いの強さ…それがあると、なかなか見つからなくてもあきらめずに探す原動力になります。
もっと自分のことをよく知りたい、自分とつながりたいという願望かもしれません。
②自分だけの「好き」「小さなモチベーション」をみつける
私の場合、「大きな好き」は”音楽”だったのですが、音楽を好きな人ってたくさんいるし、好きって言えるほどではないと思ってました。
例えば音楽が好きな人には、バンド活動を続けている人、DTM(Desk Top Music。パソコンを使って音楽をつくる)で音楽を作っている人、洋楽など無茶苦茶よく知ってる人など、たくさんの人がいます。
そういう人と比べると、”私は音楽が好き”とは言いにくい。
でも、”それをどんなふうに好きか”は自分にしかわかりませんよね。
他の人が、どんなふうにそれを好きなのかはわかりません。
もし、あなたが好きなものがあって「でもこれを好きで上手な人はたくさんいる」と思ったとしても、”どんな風に好きかは”あなただけのユニークなものです。
私の場合は、音楽を聴いているとその中のドラムやパーカッションの演奏に注目せずにはいられません。
曲がどんなリズムで、どんなグルーブで出来ているかも気になります。
たぶん、何かの楽器をしている人は、そういう傾向があると思うので、その中では特に特殊ではないかもしれませんが、感じ方はたぶん人それぞれでユニークです。
これは、音楽に限らず、言葉を紡ぐ人、絵画などのアート、手工芸、スポーツなど、どの場合も当てはまるのではないでしょうか。
特に、HSPやHSS型HSPは対象を深く感じて、考える傾向があるので、「核心のモチベーション」の感じ方はとても独特で、その人だけのものになると思います。
だからこそ、「続けられるもの」を見つけるには、ぜひ自分自身の感覚を信じること、自信をもつことが大切です。
“続ける”ためのヒント
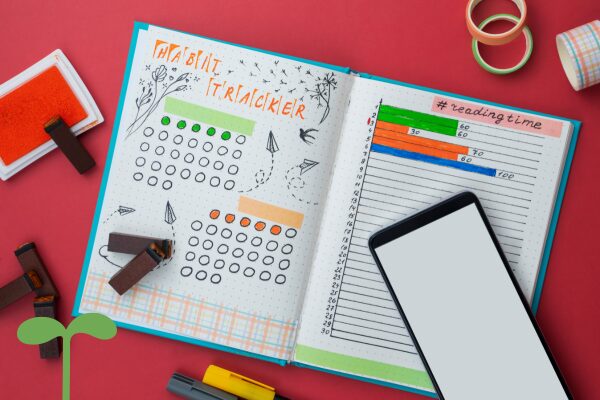
ここからは、「これなら続けられるかも」と感じられるような、HSP・HSS型HSPに合った“続け方”のヒントをご紹介していきます。
飽きること・休むことを前提に考える
HSP・HSS型HSPは、強く集中したかと思えば、急に冷める/疲れるという波が激しいことがあります。
そんな自分に「飽きっぽいな」と落ち込むより、最初から“飽きること前提”で考えるのがコツです。
- 状況によって取り組み方を変える
- 別ジャンルの中で交互に動かす(例:インプット→アウトプット)
- 季節や気分によってゆるく回す
など、変化に合わせて柔軟に調整して、やることを変化させて続けやすくします。例えば、次のような工夫が考えられます。
1.クリエイティブな活動の場合(例:ブログ・創作など)
- エネルギーがあるとき:集中して執筆/制作モードに入る
- 疲れているとき:インプット中心(本を読む、他の人の作品を眺める)に切り替える
- 季節によって:夏はアウトドアの取材、冬は屋内で編集作業中心に
2.音楽・ダンスなどの表現活動
- 集中できる時期:本格的な練習や作品づくり
- 忙しい・気持ちが落ち着かない時期:ライブやイベント鑑賞、体を動かすだけの軽い練習にする
- 花粉症や寒さなど季節的にコンディションが悪い時期:聴く側・見る側に回る
3.学びや習いごと
- 春や秋など気持ちが前向きになりやすい時期:新しいことに挑戦する
- 暑さや寒さで集中しにくい時期:復習や振り返り、記録整理など軽い作業にする
4.SNS・発信系の活動
- 気分が乗っているとき:まとめ投稿・動画収録・発信
- あまり気が乗らないとき:過去投稿のリライト/保存コンテンツの見直し
- 忙しいとき:無理せずお休み期間にしてOKとする(予約投稿でしのぐなど)
また、「飽きる」ということに関しては、同じことを続けていくと刺激がなくなってきてくるのは当たり前のことで、HSP・HSS型HSPに限らず誰にでもあります。
そんな時に”あれ?もう飽きたのかも?”、”楽しいと思ったのは間違いだった?”などと気にしすぎず、一旦軽くスルーしてとりあえず少し続けてみてください。
続けてみるとやっぱり面白かったり、次のフェーズに行けて新しい面白さを感じるかもしれません。
小さな習慣として続ける|目標を上げすぎない
やる気にあふれて高い目標を立てたのに、続かない──
HSPやHSS型HSPの人は、理想が高かったり完璧主義になりやすい一方で、刺激や疲れに敏感なため、エネルギーが長続きしにくいという面もあります。
そんな時に、ハードルを下げて習慣として続けやすくする考え方を紹介します。
「5分だけ」でいい|小さな習慣が続ける力になる
「毎日1時間勉強する」「楽器の基礎練習→応用練習まで全部やる」「毎日ブログを投稿する」──
このような頑張りが前提の目標は、モチベーションが落ちたときに継続が難しくなります。
そこでおすすめなのが、本当に小さな、簡単すぎるくらいの目標を立てることです。
- 毎日5分だけ練習する
- とりあえず楽器に触って3分間だけ音を出す
- 一文だけ書く/一行だけ読む
これくらいなら、疲れていても「そのくらいならやってしまおう」と思えて、行動に移しやすくなります。
そして実際にやってみると──
「5分のつもりが30分やっていた」「やっぱり楽しいと感じた」
そんなふうに、自然と意欲が戻ってくることも多いのです。
この方法は、「飽きたかも?」と思ったときにも有効です。
とりあえず軽くやってみる → やっぱり面白ければ続ければいいし、違うと思ったらやめればいい。
“試しに少しだけやってみる”ということが、ほんとうに飽きたのか、それとも刺激が減って少し意欲がさがっているだけなのかを知る助けになります。
やる気がなくてもできる環境を作る
さらに、取りかかるハードルを下げる環境づくりも大切です。
- 教科書や道具をすぐ手に取れるように出しておく
- アプリを開いた状態でパソコンをスタンバイしておく
- 必要なものを目につく場所に置いておく
- ジョギングなら、とりあえずウエアを着ておく
こうした「始めやすさ」があるだけで、習慣はぐっと継続しやすくなります。
高すぎる目標はNG?|HSP・HSS型HSPのための続け方
最初は小さな習慣でも、続けていくうちに「できた」という感覚(自己効力感)が育っていきます。
もちろん”いつかは○○ができるようになりたい”という高い目標があるのは素敵なことだと思います。
ただ、そこに到達するまでのステップを小さくする、ということ。
そのときそのステップをほんとに小さく、自分が思うよりももっと小さくする、ということが必要です。
その小さな積み重ねで、いつか大きな目標に到達するはずです。
※この考え方は、スティーヴン・ガイズ著「小さな習慣」を参考にしています。
自分のためになる習慣を身につけたいと思っている方にはおすすめの本です。
この内容は、下の記事でも紹介しています。
やり方や形を変えてみる
何かをやり続けているとき、「ずっと同じ方法でやる」という考えにとらわれやすくなるかもしれません。
でもHSP・HSS型HSPは、続けるのがしんどいと思った時、少し視野を広げてやり方を変えること”で続けられることもあります。
たとえば──
- ブログで発信していた内容を音声配信にしてみる
- 趣味だったイラストをSNS投稿にする → 展示にしてみる
- オンラインでやっていたことをリアルの場に移してみる
媒体や手段を変えることで、新鮮さを保ちつつ、モチベーションも復活できますね。
もしかしたら、やっていることが次のフェーズに移ったのかもしれません。
あるいは、もっと自分に合ったやり方があるのかもしれません。
やめようかな?と思った時、「形を変えて続ける」方法がないかを探してみてはどうでしょう。
「毎日やる」じゃなく「関わり続ける」にする
HSPは、疲れやすかったり体調や気分の波があったりして、毎日何かを続けるのが難しいことも多いです。
また、HSS型HSPは毎日同じことをやっていると刺激が足りず飽きる可能性もあります。
そんなときは、「毎日やる」ではなく”関わり続ける”という視点に変えるというのもおすすめです。
- 毎週でも、月に数回でもいい
- 一時期休んでも、また戻ってこればいい
- “ゼロじゃない”ことを大切にする
「途切れた=終わり」ではなく、「自分のペースで続いている」と思えると、気持ちがずっと楽になります。
続かなかった経験も「無駄」じゃないと知る
”こんどこそ!”と思って始めたけど、結局続かなかった…。
そんな経験があると、「自分はやっぱりだめだな」と感じてしまうかもしれません。
でも、“続かなかった経験”は、自分のことを知る貴重なヒントでもあります。
- どこが合わなかったのか?
- 何があればもっと続けられたのか?
- 何にワクワクして、何に飽きたのか?
こうした気づきは、自分の軸や「核心のモチベーション」に近づく手がかりになります。
いろんなことにトライしたからこそ、自分にとっての「これなら続けられる」が見えてくるのです。
「これはたぶん続かない」と思うことをやってもいい
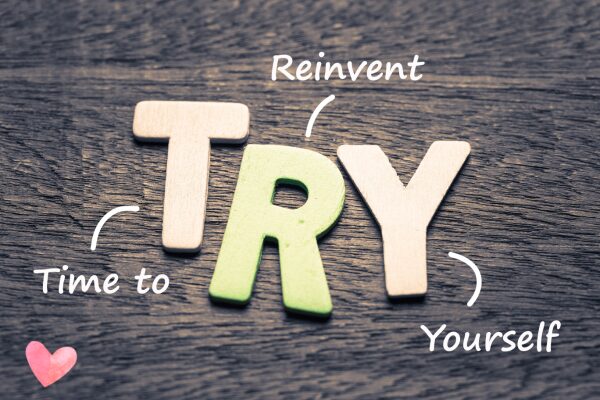
最後に、続けるためのコツではありませんが、「これはたぶん続かないかも」と思うようなことでも、そのときにやってみたいと思ったなら、やってみてもいいというお話です。
私の場合、“手芸的なもの”に、時々無性に惹かれることがあります。
たとえば、これまでやったことがあるのは──
- クロスステッチ
- かわいい布を集めてポーチなどの小物を作ること
- UVレジンでアクセサリーを作る
- 編み物
これらは過去に自分の中でブームになったものの、わりと短期間でやらなくなったものです。
クロスステッチや布小物作りの時は、海外からキットを取り寄せたり、使いきれないほどの布を集めたりして、結構お金をかけていました。
ただ、何度かそういうことを繰り返すうちに、「これは続かないやつだ!」と自分でもわかるようになってきました。
そこで、UVレジンや編み物を始めた時は、やりたい気持ちを大事にする一方で、100円ショップなどを活用して、続かなくても大丈夫なように、初期投資を抑えるように意識しました。
そのときの私にとって、興味や欲求を満たすために必要なことでした。
もし「やってみたいけど、きっと続かない気がする…」というものがあっても、やってみるのは全然アリだと思います。
その代わりに、“続かなくても大丈夫なやり方”を意識してみてください。
そうすることで、好奇心に素直になって、自分をちょっとずつ知ることができるのではないでしょうか。
まとめ
「続けられない」のは、意志が弱いからではなく、気質やモチベーションとの相性によることもあります。
特にHSP・HSS型HSPは、飽きやすさや感受性の強さも含めて、自分なりの続け方を見つけることが大切です。
この記事が、自分にあった「続けられるもの」や「続け方」を見つける参考になれば幸いです。
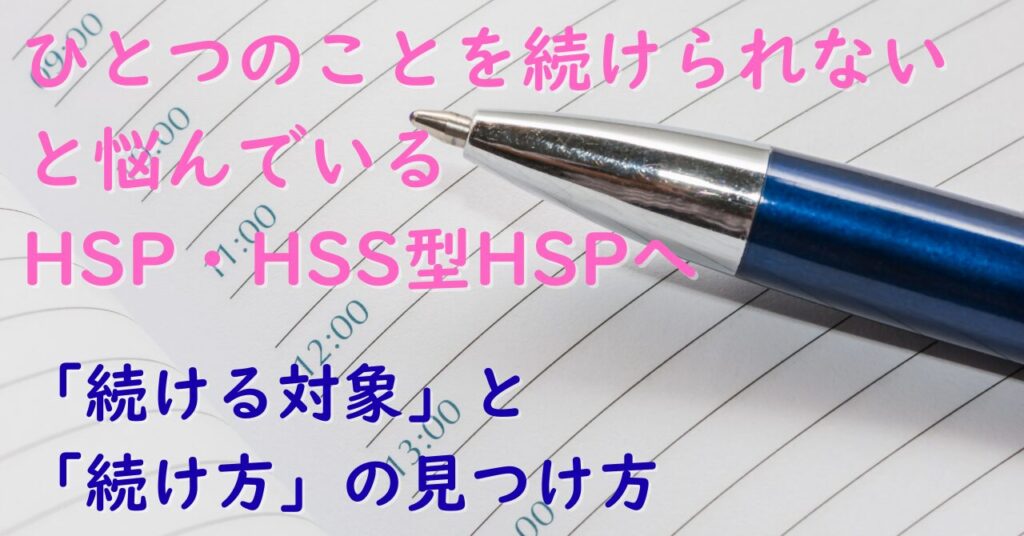





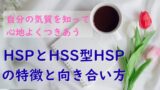


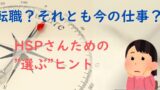


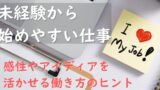


コメント