職場で「ちょっと繊細だな」と感じる同僚はいませんか。
丁寧で気配りが上手だけれど、少しの指摘で落ち込んでしまったり、急な変更に戸惑ってしまったり。
どう接したらいいのかとまどうこともあるかもしれません。
実は、その繊細さには「HSP(Highly Sensitive Person)」という気質が関係しているかもしれません。
HSPは、情報を深く処理する脳の特性を持ち、丁寧さや誠実さが強みになる一方で、刺激の多い環境では疲れやすい傾向があります。
この記事では、そんな“ちょっと繊細な同僚”と気持ちよく働くための、今日からできる小さなコミュニケーションの工夫を紹介します。
職場でみかける繊細な同僚
仕事をしていて、ちょっと敏感な人だな、と思うような同僚に出会うことはありませんか。
例えば下記の様な人などです。
- 小さな音が気になる人
- 表情や空気の変化を敏感に察する人
- ちょっとしたミスをずっと気にしている人
- 小さな指摘にでも動揺してしまう人
- 少し負荷が続くと疲れてしまう人
「いい人だけど、なんだか気を遣うな…」「どう声をかけたらいいかわからない」
そんなふうに感じるかもしれません。
もしかしたらその人は、「繊細な気質を持つ人」なのかも?
人は様々な気質を持って生まれます。例えば、「外向的」「内向的」などはよく知られています。
そういう気質の中に、「繊細で感受性が高い」という気質が存在し、この気質を持つ人をHSP(Highly Sensitive Person)と呼びます。
HSPは、周囲の刺激や人間関係に敏感に反応し、情報を深く処理する傾向があります。
そのため、細やかさや誠実さが強みになる一方で、少し動揺しやすく、刺激が多い環境では疲れやすいことがあります。
ただ、HSPは病気ではなく、まわりが特別に気を使って対応しなければいけないというものでもありません。
もしあなたが戸惑っている相手が「繊細な気質を持つ同僚」だとしたら、まずは気質が違う人だと考えてみてください。
そう思えるだけでその人の動きが少し理解できて、関わり方がぐっと楽になるはずです。
繊細さの背景にある4つの特徴

HSPの繊細さは、ただ気にしすぎているわけではなく、脳の情報処理の特性によるものと言われています。
心理学者エレイン・アーロンの研究では、HSPの気質は「DOES(ダズ)」という4つのポイントで説明されます。
- 処理の深さ
- 刺激に対する反応の強さ
- 感情の反応性と共感性の高さ
- 刺激に対する敏感さ
順番にみていきましょう。
処理の深さ(Depth of processing)
- ちょっとした出来事や情報も、背景や意味を深く考える。
- 物事を深く考える。また行動する前に情報をじっくりと分析し、先々の影響まで考慮する。
例えば、最初に全体の流れや起こりうる問題を丁寧に考え、安心してからスタートする。
本や映画を見て、数日たってもずっとその内容について考えている。など
「なかなかあの仕事始めないけど大丈夫かな?」と周りが思うとき、実は作業の流れを慎重に考えています。これにより、起こりうる問題に気がつき、あらかじめ失敗を予防できることもあります。
刺激に対する反応の強さ(Overstimulation)
- 騒音、匂い、強い光、多すぎる情報、対人関係などの刺激に強く反応して疲れやすい。
例えば、会話が飛び交うようなにぎやかな場所が苦手で、消耗する。
自分に対してでなくても、怒鳴り声を聞くとドキッとして動揺が止まらない。など。
集中するためには、落ち着いた環境が必要です。
感情の反応性と共感性の高さ(Emotional reactivity & Empathy)
- 感情が揺れやすく、さらに他人の気持ちにも強く共鳴する。
- 他人の感情をまるで自分のことのように受け取ることも多く、疲れる。
例えば、誰かがイライラしていると、自分が責められているような気がして苦しくなる。など
対人関係で疲れたり、ちょっとしたことで動揺することがあります。
ただ、どんな状況でこれが起こるかは人により、共感性の高さから、対人業務が得意な人もいます。
刺激に対する敏感さ(Sensing the subtle)
- 他の人が気にしないような光・音・におい・肌触りなど、周囲のわずかな刺激にも敏感に反応する。
例えば、人の声のトーンや、表情のほんの小さな変化にすぐ気づく。
職場でパソコンなどの機器から聴こえる小さな音、まぶしい光が気になる。など。
HSPが同僚のちょっとした変化に気づくのはこのためです。
どの程度の音や光が気になるかは人によって異なり、音は気になるけど光は平気という人もいます。(その逆も、どっちも平気という人もいます。)
こうした特徴は、めんどうな欠点ではなく、創造性や真面目さ・気配り・丁寧さなどにつながる長所にもなるものです。
ただ、刺激が多い環境では疲れやすく、感情が大きく動くこともあります。
このため、なぜそうなるかを知らない人にとっては戸惑うこともあるかもしれません。
こうした繊細な気質は、実は人だけでなく多くの動物でも見られることがわかっています。
次に、なぜ繊細なタイプが自然界にも一定数存在するのかを見ていきます。
動物にも約2割いる慎重派タイプ

HSPのように刺激に敏感で慎重なタイプは、人間だけでなく、多くの動物にも一定数(約20%)存在すると考えられています。
ある研究では、魚や鳥、哺乳類などでも、用心深く、周囲をよく観察する個体が一定割合で見られると報告されています。
一見動きが遅いように見える行動も、危険を察知して身を守るための戦略と捉えることができます。
一方で、大胆に動き、機会をつかむ個体もいます。
このように、慎重なタイプと行動的なタイプの両方がいることで、
群れ全体として生存の可能性が高まると考えられています。
現代の人間社会では、種の存続が問題になる場面はほとんどありません。
しかし、慎重で繊細なタイプと、行動力のあるタイプが共に存在することは、社会における多様性を作り出していると考えられます。
また、非常に繊細な人は約20%存在すると言われていますが、それほどではないものの”ほどほどに”繊細だと自分を考える人は20〜40%程度いるという研究報告があります。
残りの人は、自分は繊細ではないと考えているようです。
つまり、「繊細さ」という切り口で見ると、社会にはとても繊細な人、ほどほどに繊細な人、あまり繊細でない人が混ざり合っているということですね。
こうした多様な気質が集まることが、異なった才能が発揮され、社会の豊かさにつながっていくのだと思います。
繊細な同僚と働くときに役立つ対処法・コミュニケーションの工夫

相手が繊細なタイプだからといって、特別扱いをする必要はありません。
ただ、お互いが安心して働ける“橋渡し”になるようなヒントはあります。
必要なのは“優しさ”ではなく、情報・予告・透明性です。
それがあるだけで、繊細なタイプは落ち着いて力を発揮し、高品質な仕事につなげることができます。
「うちの職場ではちょっと難しいかも」「少し面倒だな」と感じることもあるかもしれません。
でも、その中で「これならできそう」と思うものがあったら、ぜひ一つでも試してみてください。
小さな工夫が、チーム全体の安心感や仕事のスムーズさにつながるはずです。
話しかける前に“ワンクッション”置く
繊細なタイプの人(HSP)は集中しているときとても深く考えるので、突然話しかけられてもすぐに戻れないことがあります。
ですので、声をかけるときには、
「ちょっと○○の件、時間あるときに話したいです。都合の良いとき声かけてもらえますか?」
「今、話して大丈夫?」
のようにワンクッションおくと、繊細なタイプもしっかり体勢を整えて話をすることができます。
それまで行っていた作業も集中して続けられるし、あなたとの会話にも集中できて結果的によいパフォーマンスが得られます。
急な変更・急な依頼は事前に一言伝える
HSPはしっかり準備して臨みたい面があります。
突然「今これ変えて」「明日までに」と言われると、一瞬パニックになってしまうことも。
突然の「急だけどお願いできる?」より、「急ぎの依頼があるんだけど、相談したい」という感じで、ちょっとした言葉の違いだけど“相談モード”で話しかけると安心します。
慎重な作業スタイルを尊重する
繊細なタイプ(HSP)は、行動に移す前に深く考え、丁寧に進め、ミスを未然に防ぐスタイルを持っています。
ただ、「もっと急いで」と言われると、質を犠牲にしてしまうようなジレンマを感じてしまいます。
そのため、「ここはそこまで丁寧じゃなくてもいいから、速さ優先で」のように、どこまで丁寧さを求めるかを具体的に伝えると、バランスがとりやすくなります。
また、「なかなか作業に取りかからないな」と感じるときは、「あの仕事、今どんな準備してる?」
と声をかけてみると、慎重に検討している内容を共有するきっかけになるかもしれません。

以前の職場で、繊細な後輩Aちゃんも、やはり仕事に取りかかる前に慎重に考えるタイプでした。
彼女は自分なりのスケジュール感を持っていて、遅れることはなかったのですが、上司から見ると不安だったようで、しばしば「もっとこうしたら? ああしたら?」と的外れなアドバイスをされていました。
私から上司に「彼女は大丈夫だから、心配しないで」と伝えたこともあります。
もっと彼女の考えをきちんと聞いてくれていれば、彼女も安心して仕事に集中できただろうと思います。
繊細タイプには一人の時間や静かな環境も必要
HSPは刺激処理量が多いので、常に人に囲まれているとキャパオーバーしてしまいます。
そのためひとりで回復する時間が必要になります。
もし、休み時間や静かなフリースペースでひとりでいたら、そっとしてあげてください。
“頑張りすぎ”を見かけたら声をかけてみる
HSPは責任感が強く、作業に集中していると自分でブレーキを踏めないこともあります。
知らないうちに頑張りすぎて疲れ切ってしまうことも…。
もし気になったら、「一旦休んだら?」「その仕事分担しようか?」など声をかけると、救われることもあります。
正確な情報で伝える
HSPは、曖昧な情報や憶測を聞くと、「どうなるんだろう?」と頭の中で様々な可能性を一気に想像してしまいます。
これは心配性というより、脳が深く処理する特性によるものです。
例えば「この案件、どうなるかわからないね」と言われると、HSPは先の展開を詳細にシミュレーションし、不安や緊張を感じてしまいます。
そのため、「まだ未確定の話なんだけど〜」「今は案の段階です」など、確定・未確定を明示してもらえると安心して行動できます。
これは正確さにこだわるのではなく、「誤解なく動きたい」だけなので、情報の段階を共有してもらえると、集中力がぐっと上がります。
急に指摘せず、背景を伝える
HSPは突然の否定や指摘に強く反応し、脳が相手の意図を深く読み取ろうとします。
そして「何が悪かったのか」「自分のせいか」と瞬時に考えてしまうところがあります。
そのため、理由や目的を添えて伝えるだけで受け取り方がまったく変わります。
例えば、「ここ違うよ、直して」ではなく、「ここは○○の意図なので、修正お願いできるかな?」のような感じです。
(ほんとに違ったら違うと言っていいです)
“なぜそうするのか”を添えることで、冷静に理解し、前向きに対応しやすくなります。
意見を言う時間の余裕を
HSPは物事を多面的に考えるため、質問や意見を求められたときにすぐに答えが出にくいことがあります。
これは優柔不断ではなく、頭の中で「相手の立場」「周囲への影響」「リスクや可能性」などを同時に整理しているからです。
そのため、少し考える時間をもらえるだけで、より的確で建設的な意見が出せます。
例えば、「少し考えて、後で意見もらえる?」のように聞くと、本人も安心するし、回答の質も高まります。

繊細な後輩のAちゃんが、慎重に考えたうえで、創造的で質の高い提案をしてくれたときの話です。
所属していたグループに、専門外の社内研修の講師を押し付けられたことがありました。
私は「それは無理!」と全力で断ろうとしたのですが、Aちゃんはじっくり考えた結果、「動画配信スタイルなら自分にもできる」という提案をしてくれました。
そして実際に見事やり遂げ、そのスタイルは翌年以降も引き継がれ、担当が専門部署に戻ってからもそのまま続いているようです。
繊細な同僚が動揺しているときに、落ち着いて声をかける
HSPは感情や雰囲気を敏感に感じ取るため、職場の緊張やトラブルなどに巻き込まれると、一時的に不安や焦り感じて動揺することがあります。
もし、繊細な同僚が動揺していて、あなたが客観的に見れている状態なら、「その案件、大丈夫。クライアントも時間に余裕あるって言ってたよ」と事実を冷静に伝えてもらえると、落ち着いて本来の力を発揮できるようになります。
どれも特別な対応ではなく、日々のやり取りの中でできることばかりです。
ほんの一言の声かけや伝え方の違いが、繊細なタイプの安心感や、お互いの気質を理解することにつながるかもしれません。
もし使えるものがあったら、少しづつ試してみてください。
まとめ
繊細な同僚との関わり方についで、繊細さの背景と、気持ちよく働くためのちょっとしたコミュニケーションのヒントをご紹介しました。
少しでも参考になれば幸いです。
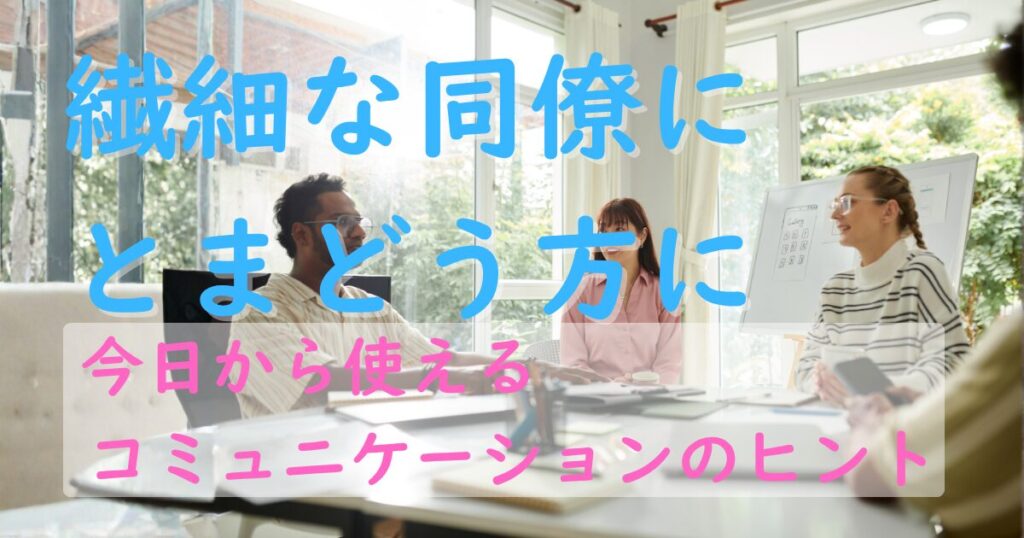





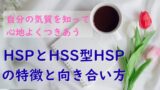


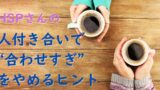
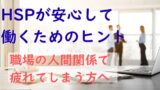


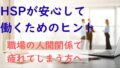

コメント