「ハーバードの個性学入門(トッド・ローズ著)」をご紹介します。
英語タイトルは「THE END OF AVERAGE」(”平均の終わり”)。
平均思考の誤りと新しい個性学ついて、たくさんの事例や研究結果を挙げて論じている本です。
主に会社や学校がどうすればひとりひとりの個性を生かせるかについて提言されており、仕事や教育の場で役立つ内容になっていますが、個人が自分の特性を考えるときに参考になることも書かれているので、ここではその部分に注目してまとめていきたいと思います。
*著者のトッド・ローズさんは、「Dark Horse 好きなことだけで生きる人が成功する時代」の作者で、今回の「ハーバードの個性学入門」はその前に書かれたものです。
「Dark Horse」の方は、個人に注目して才能を生かす方法が書かれていて、こちらもとてもおすすめです!
平均についての誤った概念
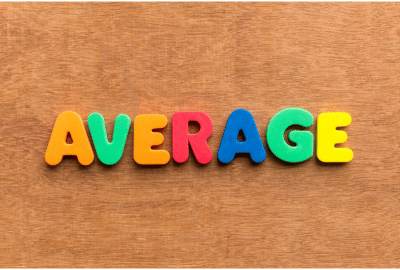
”平均”と聞くと、それが世の中の標準だと考えてしまいませんか。
平均身長、成績の平均点、平均所得、一世帯あたりの平均の子どもの数、平均の結婚年齢・・・。
平均〇〇と聞くと、自分がそれより上か下か比べてしまいます。
例えば自分の所得が平均より高ければなんとなく安心し、低ければ「そうか、平均より下なのか(;´・ω・)収入低いんだなー」と思ってしまう。
でもこの本では、指標となる様々な項目は一人の中でとてもばらついているので、単一指標の平均値で個人を評価することはできないと説明しています。
その例を下に挙げました。これは、人の体格についての調査を行った結果です
- 空軍で飛行機の事故が多発し問題になっていた。調査の結果、コクピットがパイロットの体格にあっていないのではないかという点が注目された。
- 4000人以上のパイロットの体の各部位を測定し、平均値をとって、それに合わせてコクピットを設計すれば多くの人にぴったりになるのではないかと考えた。
- 身長・腕回り・腕の長さなど10カ所を代表値として平均をとり、データの中間30%に入る場合を平均的であるとして、どのくらいの人がこの中に入るかを調べた。
- 10項目すべてが平均に納まるパイロットはゼロだった。(3つの項目で平均に納まるパイロットも3.5%に満たなかった)
参考:United States Air Force, Anthropometry of Flying Personnel by H.T.Hertzberg et al,WADC-TR-52-321 (Dayton:Wright-Patterson AFB,1954)
つまり、4063人のパイロットの体格調査結果から割り出された、平均的な体格にあわせたコクピットを作ると、それはだれにもフィットしないという結果です。
(この結果から開発されたのが、現在自動車でも当たり前に使われている、調節可能なシートです)
これはかなり衝撃的ではないでしょうか。平均、というと世の中の多くの人が含まれるようなイメージがあります。
同じことが人の才能についても言えるそうです。
才能・個性(何が得意かなど)にはばらつきがあるので、IQや試験の成績のような単一の指標では、その人が優秀かどうかは判断できない。
すべてに優れている人も、すべてに劣っている人も存在しなくて、才能はたくさんの面から評価しないとわからないのだそうです。
平均値で人を評価する方法は、1900年代の大量生産の始まった時代に、均一な労働力を確保するために世界的に広がったようです。個性的な才能の持ち主よりも、組織に適合する労働者を集められることが企業にとっては都合がよく、学校教育もそれにあわせて標準化されました。
しかしGoogleやマイクロソフトでは、以前は成績優秀者を採用していたが、その基準では求める人材が得られず、現在はその基準を放棄・修正しているのだとか。
また、今は環境も変わってきて、個性を生かすことが必要と言われるようになっています。
個性は人それぞれだということは当たり前のようにも感じますが、会社や学校などでは”標準的な能力”で人を評価するところがまだまだあります。
平均で判断することがこんなに世の中に広まっているのは、感覚的にわかりやすいからだと思います。
でも、そこには誤りがあるのです。
このことを知ることは、標準的に優れている方がよいという無意識の思い込みを手放して、自分自身の個性を知るきっかけになるかもしれません。
マイペースで学べるビデオ学習

一般的に理解するスピードが速い方が優秀だと思われがちです。
しかし、理解するスピードにもばらつきがあるのです。
社会は得意だけど、理科は苦手な人がいるのは当然ですよね。
また、同じ算数の中でも、小数点のところはすぐ理解できたけど、分数でつまずく人もいるし、その逆の人もいる。さらに、最初はペースが遅かったけど、あるところをクリアしたらぐいぐい進んで、理解の早かった人よりも応用力がついた、という人もいます。
理解のスピードは、同じ人でも何を勉強しているかによって変わってきます。
それなのに、学校ではすべての生徒に同じペースで授業をして、テストをして50点でも先に進んだりしますね(どんどんわからなくなりそうです・・・)
この問題を解決する方法として、ビデオ学習が見直されています。
ビデオ学習と言うと、本当は対面の授業の方がいいのだけど、それができない場合の代替法と言う感じがします。
ところが、対面の授業よりもビデオ授業の方が生徒がよく理解できるという報告があります。
次の動画はTEDの2011年のもので、とても注目されています。
ビデオによる教育の再発明(TEDの動画に飛びます)
サルマン・カーン「ビデオによる教育の再発明」(Youtube)
- 自分のペースで勉強に集中できる。
(わからないときは一旦停止したりもう一度みたり、退屈なところは飛ばしてみることができる) - 周りを気にせず、一人でリラックスして学べる。
(他の人はみんな理解できてる・・とわかったふりをしなくてもいい) - 学校では、ビデオ学習を宿題にして、授業では先生と生徒が今よりももっと交流して学びを深めることができる。(すでに実現されている地域もある)
- 誰でもどこにいても、ビデオ(動画)を見ることができれば学習できる。
日本でも、葉一さんがYoutubeで授業の動画を公開していて、理解できるととても人気ですね。
何かを調べていて、Youtubeの動画が分かりやすかった、という経験のある人もいるのではないでしょうか。
私は、エクセルVBAを調べていた時にYoutubeで動画を観て、とてもわかりやすくて感動したことがあります。
何かを学ぼうと学校を探すと、対面授業のところは授業料が高くて、動画授業だと安いということもありますよね。
私はこれまで、対面の方がよく学べるんだろうけど高いな~と思っていましたが、これからは心配なく動画授業のところを選ぼうと思いました!
人格特性はコンテクスト(状況・場面)で変わる

内向型、外向型、攻撃的、穏やか・・・と言った人格特性も、ひとりの人の中でばらつきがあり、コンテクスト(状況・場面など)で変わるとのことです。
例えば、職場では内向的が、家では外交的になる。
普段は穏やかだが、ある人に対してだけ攻撃的になる。
多くの場面ではとてもいい人だが、ある状況でだけ利己的になる。
まわりにそんな人はいませんか。あるいは自分について心当たりがあるかも?
あの人は内向的だ、というと、どんな時も一貫して内向的なように思われますが、そんな人はいないそうです。
自分が「~の時だけ、~になってしまう」ということがあっても、人格特性がコンテクストによっているため。しかも、コンテクストが同じなら、そのときの人格特性はとても一貫しているそうです。
人間関係では相手にとって自分がコンテクストになる
もし人間関係で、「あの人はいつもそうなんだ」という悩みがあったら、相手にとって自分がコンテクストの一部になっているのかもしれません。
この本では、相手のコンテクストを理解せず、自分のコンテクストを押し付けようとしていないか?と考えると、相手を理解しやすくなるということが紹介されています。
逆に、いつも相手には親切にするようにしているのに、あの人にだけはちょっと意地悪になってしまう・・・ということがあったら、相手の人が自分にとってコンテクストになっているということ。
そいう言うときは、”自分、だめだなぁ”と責めたりしないで、相手がどういうコンテクストなのか考える、そのコンテクストについて違う見方ができないか?と考えるなどの方が、状況を変えやすいかもしれません。
才能は特別なコンテクストで発揮されるということ
仕事で活躍できるか(才能を生かせるか)どうかも、コンテクストによって変わります。
「ハーバードの個性学」では、組織の安定した大企業で活躍していた人は、職場の環境がどんどん変動する成長過程の会社では使い物にならず、まったく業種は違うが変動の激しい職場で長年役割を果たしていた人を採用して、欠かせない人材となった例が挙げられています。
任せられると大活躍する人、他の人たちと実際に交流して才能を発揮できる人、逆にひとりでじっくり考えながらやる方が才能が生かせる人・・・、いろいろですね。
自分の才能を考えるとき、「何をするのが好きか、得意か」というところに注目しがちですが、ドット・ローズさんは「自分はどんな人間か」「人とどのように交流しているか」を知ることが成功するための土台になると述べています。
(これはドット・ローズさんの次の著作「Dark Horse」の内容につながります)
自分の隠れた才能を知りたいと言う場合は、コンテクストを含めてて「どんな状況でそれをするのが好きか、得意か」のように考えるということがヒントになりそうです。
まとめ
「トッド・ローズ著 ハーバードの個性学」から、個人が自分の特性を考えるときに役立つと思われる部分をご紹介しました。
今回ご紹介できていない内容はたくさんあります。「平均思考」が信奉されてきた歴史や、その誤りが解明された経緯、様々な事例、ひとりひとりの個性を生かすための新しい個性学に興味のある方にはおすすめの本です。
個人的には、次の著作「Dark Horse」の方が読みやすかったです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
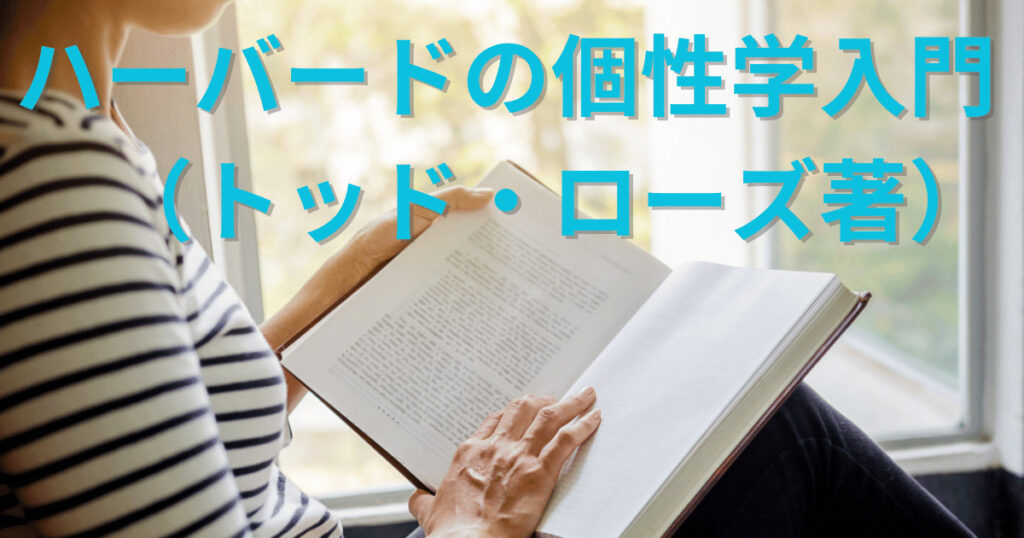



コメント