「考えたくないのに、頭の中がぐるぐるして止まらない」
「不安を手放したいのに、気づけばまた同じことを考えている…」
HSPやHSS型HSPの人は、感受性が強く、思考も深いため、ひとつのことを何度も何度も繰り返し考えてしまいがちな傾向があります。
なかなか止めることができず、疲れきってしまう──そんな方も多いかもしれません。
この記事では、そんな「不安で考えが止まらないとき」に試してほしい対処法を、HSP・HSS型HSPの気質に合わせてご紹介していきます。
また、「考えすぎてしまう」ことを否定せず、うまく距離をとりながら付き合っていくための視点もまとめましたので、ご自身の気質とやさしく向き合うきっかけになればうれしいです。
なぜHSP・HSS型HSPは「不安で考えすぎて止まらなくなりやすい」のか?

「不安でいろいろ考えすぎて頭の中が休まらない」「考えたくないのに考えてしまう」──ぐるぐる思考に悩まされるHSPやHSS型HSPは多いのではないでしょうか。
もちろん、誰でもぐるぐる思考をしてしまうことはあると思います。
でも実は、HSPやHSS型HSPには、ぐるぐる思考に陥りやすい気質的な背景があります。
HSP・HSS型HSP共通の特徴
HSPは“思考が深い”気質をもっている
HSP(Highly Sensitive Person)の特徴として、エレイン・アーロン博士が提唱した4つの特性の中に、「深く処理する(Depth of processing)」があります。
つまり、ひとつの出来事や感情に対して、思考が深く、複雑に細かく考えてしまいます。
ちょっとした会話や相手の反応をきっかけに、「本当はどう思ってたんだろう?」「あのときの言い方、怒っていたのかも」と気になって、考えが止まらなくなる。
そのうちに過去の記憶や、未来への不安まで芋づる式に浮かんできてしまいます。
共感力が高く、他人の気持ちを想像しがち
HSPの特徴には、共感性が非常に高いという面もあります。
相手の言葉や表情の微細な変化に気づいて、それを元に相手の気持ちを深く想像します。
時にはその想像が、「気にしすぎ」や「悪い方向への思い込み」につながることも。
相手に言われた何気ないひと言が、何度も頭の中でリフレインしてしまうこともあります。
未来への不安が、現実のように感じられてしまう
感度の高いセンサーを働かせて、深く考えた結果、「もしこうなったらどうしよう」「こう言ったら嫌われるかも」といった未来の想像も、HSPにとってはリアルに感じられることがあります。
そのリアルさが、脳や身体に“本当に危険が迫っている”かのような反応を起こし、不安がどんどん大きくなっていくことも起こりがち。
HSS型HSPは「不安→焦り→動きすぎ」に要注意
さらに、HSS型HSPの方は、ここに「刺激追求性(High Sensation Seeking)」が加わります。
- 不安を感じる
- すぐに何とかしなきゃと焦る
- いろいろな情報を調べたり、対処法を探したり、あれこれ試す
- でも頭の中はぐちゃぐちゃで、ますます混乱
という、“思考の過剰回転”と“行動の過集中”が同時に起きる状態にもなりやすいのです。
「あるある!」と大きくうなずいた方も多いのではないでしょうか。
次の章では、そんなぐるぐる思考の対処法について、ひとつずつ紹介していきます。
「止めようとしない」方がラクになることも

「考えすぎてつらい」「不安を止めたい」──
実はそう思えば思うほど、頭の中の“ぐるぐる思考”が止まらなくなる心理的な仕組みがあるのです。
「考えるのをやめなきゃ」がプレッシャーになる
不安や悩みごとが頭から離れないとき、「こんなふうに考え続けるのはよくない、もうやめよう」と、自分にストップをかけようとしてしまいませんか。
でも実は、「考えるのをやめよう」と意識すること自体が、脳に“考えろ”という指令を出している状態になることも。
「考えちゃダメ!」と抑えつけようとすればするほど、その対象に意識が集中してしまう──
まさに、「白クマのことを考えるなと言われると、白クマばかり浮かんでくる」現象です。
「考えてもいい」と許すことで、不思議と落ち着くことも
思考を無理に止めるのではなく、「考えても大丈夫だよ」と自分に許可を出してみると、不思議とラクになることがあります。
「この気質だから、ぐるぐるするのも当然」
「考えすぎるのも、よく観察してる証拠だからOK」
そんなふうに受け入れてあげることで、心にゆとりが生まれ、思考の渦から自然に距離が取れるようになります。
「脳のクセ」だと理解すると、冷静になれる
HSPやHSS型HSPの人にとって、深く考えすぎてしまうのは性格というよりは脳の使い方のクセとも言えます。
「また考えすぎてる」
「脳が勝手に不安シミュレーションを始めた…」
そう気づけるだけでも一歩前進です。
自分を責めずに、「また考えすぎてるね」「不安シミュレーションしてるね」とやさしく切り替えるてみてください。
考えすぎてしまう自分を、変えようとしなくていい。
それよりも、「考えてしまうのは、脳の仕組み」と知っておくだけで、ぐるぐるのしんどさは軽くなります。
次の章では、そんな思考の流れを“ふっと止める”ための、小さな習慣をご紹介します。
“脳のブレーキ”をかける小さな習慣

「頭の中が静かにならない」
「ずっと何かを考え続けてしまう」
そんなときに試してみてほしいのが、“脳のブレーキ”をそっと踏むような小さな習慣です。
ポイントは、「思考」から「感覚」へ意識を移すこと。考えるのをやめようとするのではなく、別の回路に切り替えるイメージです。
まずは体から:物理的な刺激で“今”に戻る
思考が過活性になっているとき、頭の中ばかりがフル回転して、身体の感覚を忘れてしまいがちです。
そんなときは、小さな身体刺激で注意を体に向けて、切り替える方法があります。
- 冷たい水で手を洗う
- 手首に巻いたゴムを軽くはじく
- 窓を開けて風を感じる
- 首や肩を回すストレッチ
といった、感覚に直接働きかける動作を入れることで、過剰に働いていた思考回路が一旦停止して一息つける状態になります。
五感を使って「今ここ」に意識を戻すワーク
HSP・HSS型HSPのように感覚が鋭い人にとって、五感は最大のリセットツールになります。
たとえば、こんな方法があります。
- 見えるものを3つ見つける(色や形に注目)
- 聞こえる音を3つ数える(時計の音、外の車、冷蔵庫の音…)
- 手で触れている感覚に意識を向ける(服の質感、椅子の背もたれ)
こんな風に「今ここ」の感覚に意識を戻すことで、思考の世界から一歩外に出ることができます。
1分間だけ考えるのをやめてみる
「とりあえず1分だけ考えを止めてみる」という方法もおすすめです。
とりあえず“1分間だけ”なら、意外と簡単にできます。どうしても考えがやまなければ、”1分間だけ待ってね”と心の中で言えば納まりやすいです。
1分間は、タイマーで測らなくても、自分で”大体1分”と思う間で大丈夫です。
1分間だけ、頭の中を真っ白にして何も考えないようにしてみてください。
意外にも、1分間のうちに別のことを考え始めることもあります。
もしぐるぐる思考が戻ってきても、少しだけ気持ちが整ったり、焦りがすこし抜けていたりなど、ぐるぐる考えることから抜けるきっかけになる場合も。

何も考えないのは難しいように思われるかもしれませんが、1分間なら割と簡単にできて効果があります。
私はこの方法をよく使っています。
「考えるのをちょっとだけやめてみる」、「意識を、別の感覚に移す」。
そんなちょっとした”一旦停止”の習慣が、HSP・HSS型HSPの敏感な脳にとって、大きな助けになります。
次の章では、「ぐるぐる思考」を“外に出す”ことでラクになる方法をご紹介します。
「紙に書き出す」と脳が静かになる

「ずっと同じことを考えている」
「思考が堂々巡りして、もう疲れた」
そんなとき、とてもシンプルだけど効果的なのが“書き出す”ことです。
頭の中で“渋滞”しているだけかもしれない
HSPやHSS型HSPの人は、頭の中でたくさんのことを同時に考えてしまう傾向があります。
「あれも気になる、これも不安…でも今は○○もしないと…」と、あらゆる思考がいっぺんにやってきて、脳内が渋滞状態になってしまうのです。
こうなると、考えているつもりで実はただ同じ思考が回っているだけということも。
そんなときは、「いったん全部、外に出してみる」のがおすすめです。
書くことで、脳が安心する
紙に書くという行為は、ただのメモではありません。
脳内にたまっていた思考を物理的に外に出すことで、脳が「もう覚えておかなくていい」と判断し、リソースを解放してくれるのです。
しかも、「書く=アウトプット」になることで、思考が自然と整理される効果もあります。
- 不安に思っていること
- 今日モヤモヤしたこと
- 自分に言いたいひとこと
- ぐるぐる考えた結果、こうしてみようと決めたこと
どんなことでも思っていることを“見える形”にするだけで、脳の負担はぐっと軽くなります。

脳の中身を、紙の上に全部出す感じです。
きれいにまとめなくていい
ポイントは、きれいにまとめようとしないこと。
整理しよう、わかりやすく書こう、なんて思わなくてOKです。むしろ、思い浮かんだことをそのまま書きなぐるくらいがちょうどいい。
びっくりするくらい長い文章になることもあります。
「どうしようどうしよう、でも大丈夫かも、でも怖い」みたいな支離滅裂な文でも、ちゃんと効果があります。
「不安メモ」や「ぐるぐるノート」のように、自分のためだけの思考の“一時保管場所”のように考えてください。

頭の中身を全部書いて、しばらくしたらまた次の考えが浮かぶこともあります。
そうしたら、また書きにきます!
「書くことで、自分の状態が客観的に見えて考えが整理できたり、気持ちが落ち着く」という面もあり、かなり効果あると思います。
ぐるぐる思考の対処法はあらかじめ練習しておく

ここで紹介した「ぐるぐる思考の対処法」は、実際に大きな不安に巻き込まれてしまったときに、いきなり試すのは難しいかもしれません。
そもそも、「そうだ、あの方法をやってみよう」と思い出すことすらできない場合もありますよね。
だからこそ、日ごろの小さな不安や軽いモヤモヤの段階で、気になった対処法を少しずつ試しておくのがおすすめです。
そうやって練習しておけば、自分に合った方法や、自分なりのやり方が見えてくるはずです。
そうして自分なりの対処法をいくつか持っておくことで、いざというときに「思い出せる」「すぐにできる」と思えれば、安心感にもつながります。
HSPとHSS型HSPでは、対処法に違いがある
これまで紹介してきた対処法は、HSP・HSS型HSPどちらにも効果がありますが、気質によって「ハマりやすい思考パターン」や「必要なアプローチ」に違いが出ることがあります。
同じ「ぐるぐる思考」でも、沈んでいくHSPと、暴走しかけるHSS型HSPと動きには違いがあり、必要な対処が少し違います。
HSP(非HSSの人)は「沈みやすく、引きずりやすい」
HSPの方は、もともと感情の波を深く受け取りやすい傾向があります。
- 誰かのひと言が気になってずっと引きずる
- 自分のせいかもしれないと考えてしまう
- 不安を感じると「またダメかも」と思考が沈んでいく
このように、感情と結びついた思考ループに入りやすく、気づいたら自己否定になっている…ということも少なくありません。
そんなHSP(非HSS)の方向けの対処のポイントは下記の通り。
思考から距離を取る練習をこまめにやってみる
自分をやさしく外側から見るような視点を取り入れると、感情に巻き込まれにくくなります。
- 五感を使って「今ここ」に戻る
- 不安メモなどで頭の外に出す
- セルフコンパッション(「それだけつらかったんだね」と声をかける)
HSS型HSPは「動きたくなる」「焦って空回りしやすい」
HSS型HSPの人は、HSPの繊細さに加えて、HSS(刺激追求性)のため下記のようになりがちに…。
- 不安を感じる → とにかく動いて解決しようとする
- あれこれ調べたり、試したり、手を出しすぎて混乱
- 頭の中も、行動も、空回り状態に…
”すぐになんとかしようとする”のはあるあるではないでしょうか。
そんなHSS型HSPの方向け、対処のポイントはこちら。
“静止”の練習と、動き出す前の一呼吸
HSS型HSPには“いったん立ち止まる”ことがおすすめです。
「1分だけ考えるのをやめてみる」や「深呼吸して足の裏を感じる」といった、脳と身体にブレーキをかける動きを取り入れてみてください。
さらに、不安に駆られて動く前に、「自分は何が怖いのか?」「本当は何を望んでるのか?」と問いかけて、焦りではなく“自分軸”から行動なのかを考えてみるといいかもしれません。

(HSS型HSP)
私も、ほんとにこれです。
「すぐに何とかしたい!」と思ってマッハで動いてしまう。すぐ解決しないと気が済まないんですよね。
後からみると、無駄な動きの連続です。
世の中には、”すぐに何とかしなくても構わない人もたくさんいる”ということを知った時は驚きましたが、そいういうものかと参考にもなりました。
ぐるぐる考えたからこそ、解決にたどり着くこともある

ここまで、「思考が止まらないときの対処法」をいろいろ紹介してきました。
でも実は、ぐるぐる考えること自体が「悪いこと」だとは限りません。
HSPやHSS型HSPの人が「考えすぎる」のは、言い換えれば、物事を深く、丁寧に、誠実に考えようとしているからでもあるのです。
考えすぎ=悪ではない
「また考えすぎてる」「自分はネガティブだ」と思ってしまうかもしれませんが、その“考えすぎ”があったからこそ、他の人が気づかないことに気づけたり、納得できる答えにたどり着いたりすることもあります。
- 「悩んで悩んで、ようやく本音が見えてきた」
- 「ぐるぐるした末に、『これは違う』と気づけた」
- 「誰かに話したら、思った以上に整理されていた」
そんな経験がある方もいるかもしれません。
HSP・HSS型HSPの「深い思考」は本来の強み
深く考える力は、HSPやHSS型HSPの強みである洞察力・分析力・共感力・創造力にもつながっていきます。
- HSPは、微細な違和感を言語化できる人が多い
- HSS型HSPは、深い思考と広い好奇心の掛け算で、ユニークな発見に至ることも
ぐるぐる思考の“先”にこそ、あなたらしい答えがあることもあるのです。

私もぐるぐる考えたからこそ、自分なりの正解にたどり着くことはあります。
仕事で問題が起こった時、家に帰ってから考え続けてしまっても、その結果「そうか!こうすればいいんだ」と思いつきました。それで、出勤した日にすぐ対応することができたこともあります。
また、不安に駆られてぐるぐるが止まらずネット検索もしまくった結果、心配していることが起こる確率はすごく低いことが分かったということもあります。
“考える力”と“ぐるぐる思考”のバランスをとる
そうは言っても、ぐるぐる思考は、本当は別のことに集中したいときやリラックスしたいときにも、ものすごく時間を取ってしまいます。
考えたくないのに考えてしまうというのは、とても苦しいですよね。
基本的には、ぐるぐる思考とうまく距離をとって、巻き込まれすぎないようにすることが一番だと思います。
そのために、この記事で紹介したような対処法は、きっと役に立つはずです。
ただ、HSPやHSS型HSPの場合、ぐるぐる考えてしまうことにも理由や背景があるということを知って、
少しやさしく、“考えてしまう自分”を見てあげられたら、きっと自分を肯定しやすくなって、バランスも取りやすくなるのではないかと思います。
まとめ
不安にかられて、ぐるぐると考えてしまい止められない時の対処法をまとめました。
考えすぎてしまうのは、HSPやHSS型HSPの繊細さや深さがあるから起きやすいという面もあります。
ぐるぐる思考とうまく距離をとりながら、自分の気質とやさしく付き合っていくと楽になるかもしれません。






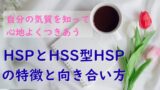
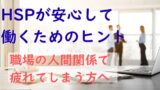








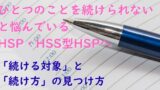

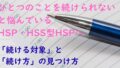

コメント